
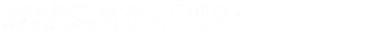
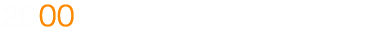
2000.06
タイトル: 障害理解教育の模擬授業経験学生の意識
著 者 : 近澤真由・真城知己
所 収 : 草の根福祉(社会福祉研究センター紀要), 第31号, pp.141−149.
<要旨>
障害理解教育の模擬授業への取り組みに参加した学生に対する調査をもとにその経験によって「学習したと考えていること」模擬授業への参加の際に「考えたこと」及び「今後さらに学習したいこと」について意識の内容を整理した。その結果,障害理解教育の奥深さや必要性を十分に意識するとともに各自の知識の不十分さが自覚され,「障害」に関する学習をより積極的に行いたいという強い意欲が喚起されていたことが明らかとされた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
2000.02
タイトル: 21世紀に向けたイギリスにおける特別な教育的ニーズへの対応
著 者 : 真城知己
所 収 : 養護学校の教育と展望, No.116, pp.52−57
<要旨>
本稿では,イギリスにおける「特別な教育的ニーズ」への対応の展開について,制度的展開について述べた上で,緑書「すべての子どもに優れた教育を(Excellence for all children) 」,「特別な教育的ニーズへの対応(SEN行動計画)」「特別な教育的ニーズ裁定委員会(Special Educational Needs Tribunal:SENT)」及び「SENコーディネーター(Special Educational Needs Coordinator: SENCo)」について取り上げて,21世紀に向けた最新の動向と課題について論じた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
2000.02
タイトル: 千葉県における現職教員の大学での研修機会への要望に関する一考察
ー特殊教育諸学校,特殊学級及び通常の学級の教員への調査ー
著 者 : 真城知己
所 収 : 千葉大学教育学部紀要(教育科学編), 第48巻, pp.139−155
<要旨>
本論文では,大阪府下において行った研究をふまえ対象を特殊学級及び通常の学級担任に拡大して実施した調査の報告を行った。分析は所属学校学級種別の比較,学習形態別の比較,及び総教職経験年数と特殊教育諸学校の経験年数の各観点から行った。結果として「情緒面」「ことば」「事例」「最新情報」を上位とする全体的な要望の強さが確認された。経験年数の短い教員ほど要望の強い傾向も認められた。ただし,経験年数の長い教員でも要望が低いわけではなく,常に最新の指導法や知見を継続的に学習できる機会を多様に保障することの重要性を指摘した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
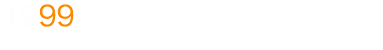
1999.03
タイトル: 障害児教育教員養成課程学生の副詞形職業への就職志望について
著 者 : 真城知己・近澤真由
所 収 : 大阪教育大学障害児教育研究紀要, 第21号, pp.17-33
<要旨>
本研究は,障害児教育教員養成課程に所属する学生で教員以外の進路(特に福祉職)をとるものが増加していることを背景に,今後の進路指導を検討するために計画された。学部2~4回生を対象に,入学時の志望学部,入学時と現在の志望進路,希望する仕事の性格,就職への支援に関する大学への要望,及び就職に向けた準備状況について質問紙による調査を行った。その結果,入学時点ですでに希望進路が教育系と福祉系に二分されていたことが明らかとなった。入学後は特殊教育諸学校教員を志望する学生が漸増する傾向が認められたが,採用試験枠の急減を受けて福祉系職種を志望し,その方面への就職情報の提供を強く求める傾向も確認された。課題として,就職に向けた準備が非常に遅く,早い学年から系統的な進路指導を行う必
要性が指摘された。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1999.01
タイトル: 肢体不自由養護学校における作業学習での工夫に関する一考察
著 者 : 向井敦・平野聖子・真城知己
所 収 : 大阪教育大学紀要第Ⅳ部門教育科学, 第47巻第2号, pp.425-433
<要旨>
本論文では,精神薄弱教育において開発された作業学習が,肢体不自由教育においてどのような独自性をもつのかを明らかにすることを目的とし,特に作業学習の「工夫」に注目して検討した。作業学習の内容は,木工や農業,陶芸など,精神薄弱教育での活動内容と変わらなかった。作業工程や作業分担における工夫や自助具・補助具・道具の工夫,時間的配慮の実施等が確認され,これらが肢体不自由教育の特徴と考えられた。こうした工夫の結果,作業の正確性の向上,作業能率の向上,製品の質の向上に加え,生徒の意欲向上や作業姿勢の改善などがその効果として評価されていた。今後の課題として,生徒のもつ運動障害への配慮と知的障害への配慮がそれぞれ独立して行われるのではなく,両者の相互関係を考慮した配慮について一層の検討が必要であることを指摘した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
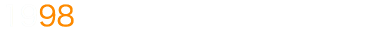
1998.11
タイトル: 大阪府下の特殊教育諸学校教員の大学における教員免許状取得への要望に関する調査
著 者 : 真城知己
所 収 : 発達障害研究, 第20巻第3号, pp.91-97
<要旨>
大学における特殊教育諸学校教員免許状の取得機会の充実を図る資料を得るために,聾学校及び養護学校教員330名を対象に調査を行った。その結果,年齢の若い教員ほど免許状の保有率が低く,取得形態では認定講習と特殊教育特別専攻科の希望順位が高かった。ただし,認定講習を最下位に評価する教員も多く両極傾向がうかがえた。大学に在籍すると想定した場合の教員免許状の取得に関する希望を,マーケティング領域で使用されているコンジョイント分析の手法を応用して分析したところ,課程の形態や年限などの要因と比較して遙かに校務からの専従免除が求められている状況が明確となった。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1998.08
タイトル: 特殊教育諸学校教員の大学における現職研修機会への要望の検討
-大阪府下の聾学校及び養護学校教員への調査-
著 者 : 真城知己
所 収 : 大阪教育大学紀要第Ⅳ部門教育科学, 第47巻第1号, pp.139-152
<要旨>
大阪府下の聾学校及び養護学校教員を対象に,大学における現職研修機会に対する要望調査の結果を報告した。大学院及び特殊教育特別専攻科(正規課程)と公開講座それぞれの場合について15項目の研修内容に対する評定結果を分析した。その結果,学校種間での有意差は認められなかったこと,全般的に学習への要望が強いが「情緒面」に関する希望が特に強く,また,全体としては公開講座よりも正規課程での学習への要望が強く,さらに年齢層によって希望する内容が異なっている(20代では指導法,50代では実践の位置づけなどへの関心がより高かった)ことなどが明らかにされた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1998.07
タイトル: 19世紀ロンドン慈善組織協会(COS)のラグド・スクールの役割への認識
著 者 : 真城知己
所 収 : 関西教育学会紀要, 第22号, pp.146-150
<要旨>
19世紀末にイギリスの慈善組織協会が肢体不自由児への教育の有効性について社会的喚起を促した際に取り上げたのは実業学校であった。ラグド・スクールはその前身の一つであり,最貧困層の家庭の子どもを対象にした学校であった。実業学校は「防貧」が主目的ではなかったが,慈善組織協会はこの点から肢体不自由児への有効な処遇策の一つとして評価したのであった。ラグド・スクールについても同じ観点からとらえられた可能性が高く,慈善組織協会が防貧の手段として教育の意義を認識する契機となったことが考えられたことから,機関誌を史料として検討した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
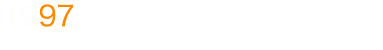
1997.03
タイトル: 特別な教育的ニーズの評価の視点
-イギリスの動向を手がかりに-
著 者 : 真城知己
所 収 : SNEジャーナル, 第2巻, pp.3-29
<要旨>
特別な教育的ニーズの概念は,個体内要因への偏重から環境要因とその相互作用を視点として取り入れたことが特徴であるが,1981年教育法のもとではこの点をふまえた評価は十分ではなかった。現行の1993年教育法と施行規則及び施行細則の枠組みの中で,評価がどのような特徴と課題をもっているのかを整理した。具体的には,施行規則,施行細則及び実際の評価パッケージの例を検討対象として,特徴を整理したとともに,今後の方向性について課題となる視点を述べた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1997.02
タイトル: イギリスにおける特別な教育的ニーズをめぐる制度的課題
-1993年教育法以前の地方教育当局の判定諸作成における課題-
著 者 : 真城知己
所 収 : 大阪教育大学障害児教育研究紀要, 第19号, pp.37-50.
<要旨>
イギリスにおいては,1981年教育法の施行後,地方教育当局の特別な教育的ニーズに関する「判定書」の作成が全般に低率である上に地方教育当局ごとの格差が拡大する事態が生じた。本稿では,1993年教育法の施行以前の時期を検討対象とし,特別な教育的ニーズ概念の制度的導入を支える財政的保障の欠如の問題に加えて,地方教育当局と学校との関係をめぐる制度的問題について,現行法である1993年教育法の特別な教育的ニーズ関係の規定にも影響を与えたAudit Commission and HMIによる2つの報告書の勧告もふまえながら検討を行った。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
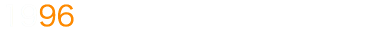
1996.09
タイトル: イギリスにおける慈善組織協会の障害児教育への貢献に関する研究
-肢体不自由教育への意義を中心に-
著 者 : 真城知己
所 収 : 特殊教育学研究, 第34巻第2号, pp.21-32.
<要旨>
19世紀後半にイギリスの都市部の貧困問題の解決を意図して設立された慈善組織協会(C.O.S.)が障害児教育の領域に対しても重要な提言をしていたことが知られている。本研究では,特に肢体不自由児者への慈善的対応の限界と彼らへの教育の必要性が主張されるに至る過程を検討した。その結果,1)C.O.S.は肢体不自由児者も自助努力を払うべき対象として基本的に例外扱いはしなかった,2)教育は慈善的救済での対応の限界の打破の一手段として考えられた,3)肢体不自由児者に対する実業教育が一定の成果をあげていた一方で4)何の対応もなされないままにされている肢体不自由児者が多数いることを社会に公にしたことの意義が認められた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1996.06
タイトル: イギリス19世紀後半の Industrial Schoolと肢体不自由児
ー Cripples' Home Industrial School for Girls, Marylebone Road についてー
著 者 : 真城知己
所 収 : 関西教育学会紀要, 第20号, pp.91-95
<要旨>
イギリスにおいて肢体不自由児に最初の組織的な教育を行った女子肢体不自由ホーム・実業学校は,肢体不自由児を対象にした施設で唯一Industrial Schoolとしての認可を受けた学校でもあった。本研究ではこの学校に焦点をあて,①生徒の構成及び治安判事命令による強制収容措置者の割合,及び②教育活動の状況について,視学官報告を史料に検討した。その結果,この施設ではIndustrial Schoolとして強制収容措置者を引き受けることをあまりせず,生活態度への配慮は行いつつも,もっぱら肢体不自由児への職業教育に重点をおいていたことが明らかとなった。また,生徒の障害の程度は,身辺自立の世話を貧民収容による生徒に求める必要のある場合もあったが,一定の作業能力のあるという意味で「軽度」であることが理解できた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1996.03
タイトル: イギリスにおける特別な教育的ニーズ概念の教育制度への位置づけに関する研究(1)
-1981年教育法案審議の分析-
著 者 : 真城知己
所 収 : 兵庫教育大学研究紀要, 第16巻第一分冊(学校教育・幼児教育・障害児教育), pp.101-108
<要旨>
1981年教育法によって制度的に導入された特別な教育的ニーズの概念の導入背景は現在でも明確にされていない。本研究では1981年教育法案における同概念の定義に関する原案と修正案の審議の焦点を明らかにすることで同概念の導入がどのような問題の解決を意図されていたのかを探ろうと試みた。しかし結果として,特別な教育的ニーズの定義に関する議論では,背景となる問題状況にふれられることなく,単に対象の範囲についての議論に始終していたことが明らかとなった。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
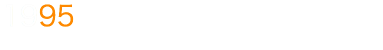
1995.03
タイトル: イギリス1993年教育法の特別な教育的ニーズを持つ子どもに関する規定
著 者 : 真城知己・名川勝
所 収 : 筑波大学リハビリテーション研究, 第4巻第1号, pp.69-73
<要旨>
イギリス1993年教育法第3部(特別なニーズを持つ子ども)は新しい障害児教育の枠組みを提供した1981年教育法におきかわるものである。従ってその規定は80年代特有の実践的課題を背景に持つ。しかし同時に同法は教育への市場原理の導入を図る1988年教育改革法の路線を継承する憂慮すべき性格も持つ。本稿ではこの第3部の規定の概要を紹介するとともに1981年教育法からの修正条項の整理をした。また同法の抱える課題にも触れた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
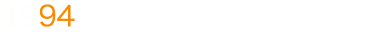
1994.11
タイトル: 19世紀末イギリス公立基礎学校における肢体不自由児
-在籍率とそのとらえられ方-
著 者 : 真城知己
所 収 : 特殊教育学研究, 第32巻第3号, pp.49-56
<要旨>
19世紀末に行われたWarner,Fによる2回の調査での公立基礎学校における肢体不自由児の出現率は約0.3%であった。この値が救貧法学校等の場合よりも小さいのは①一般的な授業料納付困難状況,②学務委員会が通学手段確保の費用支出権限を持たなかったこと,及び③保護者の意識の3点に要因が求められた。また,公立基礎学校においては「肢体不自由」という一次的障害ではなく,二次的に発生した学習の遅れに焦点があてられており,肢体不自由児の在籍は教育上の積極的理由に基づくものではないことが明らかにされた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1994.08
タイトル: イギリス19世紀末の精神遅滞特殊学級に在籍した肢体不自由児
-「欠陥児・てんかん児委員会」における教師等の証言-
著 者 : 真城知己
所 収 : 関西教育学会紀要, 第18号, pp.104-109
<要旨>
19世紀末イギリスの軽度精神遅滞特殊学級には学習上の遅れを示す肢体不自由児も在籍していた。そこでは精神遅滞と学習上の遅れの区別が行われたものの,実際には後者にのみ対応がなされた。肢体不自由児独自のニーズへの対応として姿勢保持用の特別なイスが用意された場合もみられたが,こうした配慮の背景に「出来高払い制」の影響が示唆された。このことは出席状況に応じた補助金支出の構造が問題となるという旨の証言を特殊学級の担任教師が行っていたことからもうかがわれた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1994.03
タイトル: 肢体不自由養護学校高等部における作業学習の位置づけに関する予備的考察
-教育課程上の設定の状況と実践例の検討-
著 者 : 真城知己
所 収 : 兵庫教育大学障害児教育実践研究, 第2巻, pp.21-34
<要旨>
本研究では全国の肢体不自由養護学校高等部を対象に作業学習の位置づけに関して,教育課程上の設定の状況及び実践例について検討を行った。作業学習の設定の状況については,教育課程の類型化における領域・教科をあわせた指導の設定状況との関わりから検討し,運動障害に加えて知能障害を合併する生徒に対して精神薄弱養護学校の教育課程を運用できる特例措置にもとづいた類型の適用に限界があることが示唆された。そして運動障害と知能障害の相互関係を視点に加えた指導類型の開発の必要性を指摘した。また,実践例からもこうしたニーズの存在を指摘した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1994.03
タイトル: 高等部のみを設置する精神薄弱養護学校における職業教育をめぐる状況の検討
著 者 : 真城知己・名川勝
所 収 : 職業リハビリテーション, 第7巻, pp.9-16
<要旨>
本研究では,高等部のみを設置して主として職業教育を行う精神薄弱養護学校を対象とし,設置学科,職業関係教科等の教育課程上の位置づけ,職場実習,及び進路についてその特徴を整理し,検討を加えた。その結果,これらの精神薄弱養護学校では,大半の学校で職業教育に関する学科ではなく普通科が設置され,系統的な現場実習行われていたことが明らかとなった。そして,ある程度の実践を積んできた学校では在籍生徒の障害の程度の変化に伴って一つの過渡期にさしかかっていることを指摘した。なお,本研究は平成5年度文部省科学研究費補助金の助成をうけて行われた研究の一部である。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
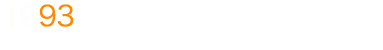
1993.03
タイトル: イギリスにおける特別な教育的ニーズ概念の導入背景に関する一仮説
-中等教育改革を背景にした説明の試み-
著 者 : 真城知己
所 収 : 障害者の教育と福祉, pp.10-26
<要旨>
イギリスにおいては「1981年教育法」の施行に伴って従来の障害のカテゴリーが制度的に撤廃され,それに代わって新たに特別な教育的ニーズの概念が導入された。この概念の導入に伴って特殊教育の対象者が従来の10倍ともなる見積もりが行われたことを糸口に,特別な教育的ニーズ概念の導入背景について一般の学校,特にコンプリヘンシヴ・スクールの発生とその台頭の過程で生じた問題と関連づけながら仮説提起的に要因の説明を試みた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
1993.03
タイトル: アメリカ合衆国に見られる障害を持つ青年に対する移行活動の現状と課題
著 者 : 真城知己
所 収 : 職業リハビリテーション, 第6巻, pp.45-52
<要旨>
本研究では中等教育とその後の職業生活をはじめとした地域生活を結ぶ概念としての移行活動に注目し,顕著な活動の見られるユタ州及びオレゴン州の例を取り上げて現状と課題の検討を行った。そして継続的なサポートの必要性や,個別のニーズを把握して移行活動におけるコーディネートを専門とする職種の開発,及びそうした専門家よりなる組織を支える行政当局による活動や制度的な保障を確立する努力が必要であることを指摘した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
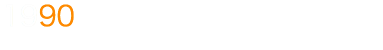
1990.12
タイトル: イギリスにおける特別な教育的ニーズを持つ青年に対する継続教育について
著 者 : 真城知己・石部元雄
所 収 : 筑波大学心身障害学研究, 第15巻第1号, pp.63-72
<要旨>
イギリスにおける継続教育は,実際の在籍者数こそ少ないものの,特別な教育的ニーズを持つ青年にとっては義務教育後の教育機会の一つとして注目されるものである。本論文では,特別な教育的ニーズを持つ青年に対して開講されている継続教育について,法的背景やその課程の種類,職員養成等の問題を明らかにするとともに,現行法である「1988年教育改革法」の施行に伴って生じることが予想される今後の課題について述べた。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置
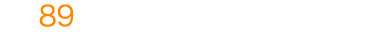
1989.12
タイトル: 戦後のイギリス特殊教育に関する一考察
ーウォーノック報告に焦点をあててー
著 者 : 真城知己・石部元雄
所 収 : 筑波大学心身障害学研究, 第14巻第1号, pp.91-98
<要旨>
本論文では,イギリスにおいて1978年に提出された「ウォーノック報告」に焦点をあて戦後のイギリス特殊教育における問題点を整理するとともに,様々な専門領域が関与するようになり,ますます複雑さを増す現代の特殊教育について,再度「教育」という観点から見直す必要があることを指摘した。
ここに「ダウンロードパーツ(編集時の「その他」から選べる)としてPDFファイルを配置


 前のページへ
前のページへ